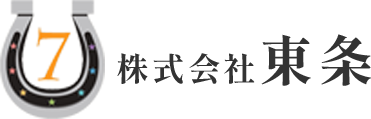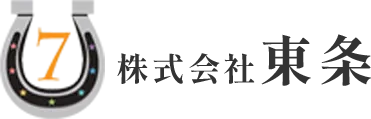営業の現場で役立つクレーム対応の基本原則と信頼構築のコツ
2025/10/12
営業の現場でクレーム対応に悩んでいませんか?クレームが発生すると、顧客との信頼関係や営業成績に大きな影響を与えることがあります。うまく対応できないと、不満が増幅し、営業活動自体にもストレスがかかりがちです。本記事では、営業の現場ですぐに活用できるクレーム対応の基本原則と信頼構築のコツをわかりやすく解説します。より効果的な営業活動を実現し、顧客の満足度や自身の成長を実感できる実践的な知識が得られるでしょう。
目次
営業現場で実るクレーム対応の極意

営業クレーム対応の基本手順と心構え
営業の現場でクレーム対応を成功させるためには、まず冷静な心構えと段階的な対応手順が欠かせません。クレームが発生した際は、顧客の感情を受け止め、相手の話を最後まで傾聴することが第一歩です。その上で事実確認を丁寧に行い、誤解やミスが発生していないかを見極めます。
クレーム対応では、感情的にならず、謝罪の意志を明確に伝えることが重要です。たとえ自社に非がない場合でも、お客様の不満や怒りに共感し、誠意を持って対応することで信頼回復への第一歩となります。事実確認後は、解決策や今後の対応方針を迅速かつ具体的に伝えましょう。
例えば、商品納期の遅延によるクレームの場合、まず謝罪し、遅延理由と今後の対応を明確に説明します。このように、クレーム対応の基本手順を守ることで、顧客との信頼関係を維持しやすくなります。営業活動におけるストレス軽減や成績向上にもつながるため、日々の実践が大切です。

営業でよくあるクレームの発生原因とは
営業現場で頻発するクレームの多くは、納期遅延や商品・サービス内容の認識違い、説明不足などが主な原因です。顧客とのコミュニケーション不足や、情報伝達のミスによって誤解が生じやすくなります。特に、事前の期待値調整が不十分な場合にトラブルが発生しやすい傾向があります。
また、営業担当者の知識不足や確認作業の甘さも、クレーム発生の大きな要因となっています。例えば、契約内容やサービス範囲についての説明が曖昧だった場合、顧客は「聞いていた話と違う」と感じやすくなります。こうした事例は、営業でのクレームが多い理由の一つです。
このような発生原因を把握し、事前に対策を講じることで、クレームの予防につながります。定期的な情報共有や確認作業、明確な説明を徹底することが、営業活動の質向上と顧客満足度向上に直結します。

営業クレームでやってはいけないNG例
クレーム対応で絶対に避けるべきNG例として、顧客の話を遮る、言い訳や責任転嫁をする、感情的に反論する、などがあります。これらの行動は、顧客の不満を増幅させ、信頼を損なう原因となります。特に、非がない場合でも「それは当社の責任ではありません」と突き放す対応は、顧客の印象を悪化させます。
また、返金や値引き要求に対し、即座に断る、説明不足のまま対応を終えるのもNGです。たとえば「ルールですから」と一方的に返金を断ると、顧客の納得感を得られません。こうした対応は、営業マン自身がクレームを気にしすぎて落ち込む原因にもなります。
失敗例として、電話で声を荒げたり、謝罪を後回しにしてしまったことで顧客の怒りが収まらず、取引停止に至ったケースがあります。NG行動を避け、誠実な対応を心がけることが営業現場での信頼構築の第一歩です。

営業現場で役立つクレーム対応4原則
営業クレーム対応には「迅速な対応」「傾聴と共感」「誠意ある謝罪」「事実確認と説明」の4原則が有効です。まず、クレームが発生したら即座に対応することで、顧客の怒りや不安を和らげることができます。次に、相手の話をしっかりと聞き、感情に寄り添う姿勢を示すことが信頼につながります。
誠意ある謝罪は、非がある場合はもちろん、非がない場合でも「ご不快な思いをさせて申し訳ありません」といった共感の言葉が効果的です。そして、事実確認を徹底し、顧客に分かりやすく説明することが重要です。これらの原則を守ることで、クレーム対応が上手い人と評価されやすくなります。
例えば、営業現場で「納品が遅い」とクレームを受けた場合、まず謝罪し、遅延理由と今後の対応スケジュールを丁寧に説明することで、顧客の信頼回復につなげることができます。4原則を実践することで、クレーム対応のストレスも軽減されるでしょう。

営業クレーム対応で信頼を築くポイント
営業現場でクレーム対応を通じて信頼を築くためには、誠実な姿勢と一貫したコミュニケーションが不可欠です。クレームが発生した際は、まず顧客の感情に寄り添い、迅速に対応することが大切です。さらに、解決までの進捗を逐一報告することで、顧客の安心感を高めることができます。
信頼構築のもう一つのポイントは、クレームを成長のチャンスと捉え、再発防止策を積極的に提案することです。例えば、クレームを受けた内容を社内で共有し、業務改善に活かす姿勢を見せることで、顧客からの評価も高まります。こうした積み重ねが、営業マンとしての成長や顧客満足度向上につながります。
顧客から「またこの人に任せたい」と思ってもらえるような対応を心がけることで、長期的な信頼関係を築くことができます。クレーム対応で悩んでいる方は、ぜひ本記事のポイントを実践してみてください。
信頼関係を深める営業のクレーム処理法

営業で信頼を得るクレーム対応のコツ
営業現場でクレーム対応を行う際、最も重要なのは「初動の迅速さ」と「誠実な謝罪」です。クレームが発生した場合、まずはお客様の話を最後まで丁寧に聞くことが信頼構築の第一歩となります。感情的にならず、相手の主張や不満をしっかり受け止める姿勢が大切です。
速やかな対応が信頼回復のカギです。対応が遅いと、お客様の不満や怒りが増幅しやすく、営業としての評価にも影響します。たとえば、電話やメールで即座に状況確認と謝罪を行い、ミスの原因や今後の対応を明確に説明することで、顧客の安心感を高めることができます。
また、事実確認を怠らず、必要に応じて関係部署と連携しながら解決策を提示しましょう。失敗例として、曖昧な説明や責任逃れは信頼喪失につながります。成功例では、迅速な謝罪と再発防止策の共有により、逆に信頼が強化されたケースも多く見られます。

営業クレーム対応が上手い人の特徴解説
営業でクレーム対応が上手い人には共通する特徴があります。まず、冷静さを保ちつつ、相手の感情に配慮したコミュニケーションを取る力が挙げられます。お客様の怒りや不満を受け止めつつ、感情的にならずに対応することが求められます。
また、問題解決力も重要なポイントです。事実確認を徹底し、原因を明確にしたうえで、適切な対応方法を提示できることが信頼につながります。さらに、謝罪や説明の際に曖昧な表現を避け、具体的な解決策や今後の対応を明確に伝えることができる人は、顧客満足度も高い傾向にあります。
実際に、クレーム対応が上手い営業は「クレーム=成長のチャンス」と捉え、経験を次に活かしています。例えば、返金や値引き要求などの難しいケースでも、会社の方針や理由を丁寧に説明し、誠意ある対応を心がけることで、信頼を勝ち取っています。

顧客との信頼構築に必要な営業対応術
顧客との信頼関係を築くためには、日頃からの誠実な営業対応が不可欠です。クレーム対応時だけでなく、普段から丁寧な説明や迅速なレスポンスを心がけることで、顧客からの信頼が得られやすくなります。
具体的には、商品の内容やサービスの詳細を事前にしっかり説明し、誤解やトラブルを未然に防ぐことが大切です。万が一トラブルが発生した場合も、事実を隠さず、会社としての見解や再発防止策をしっかりと伝えることで、顧客の安心感を高めることができます。
また、クレームが発生した際のフォローアップも重要です。問題解決後も定期的に連絡を取り合い、顧客の満足度を確認することで、長期的な信頼関係につながります。こうした地道な積み重ねが、営業活動全体の成果を高めるポイントとなります。

営業現場で活きる共感力と伝え方の工夫
営業のクレーム対応では、共感力と伝え方の工夫が成果を大きく左右します。お客様の感情に寄り添う姿勢を示すことで、不満や怒りを和らげることが可能です。「そのお気持ち、よく理解できます」などの言葉を添えることで、相手は話を聞いてもらえていると感じやすくなります。
伝え方のポイントは、わかりやすく、誠実な説明を心がけることです。専門用語を避け、誰にでも伝わる言葉で状況や対応策を説明しましょう。失敗例として、説明が抽象的で要点が伝わらなかった場合、顧客の不安を増幅させてしまうことがあります。
一方、成功している営業担当者は、非言語コミュニケーションも活用しています。表情や声のトーン、姿勢などを意識することで、言葉以上に誠意が伝わります。これらの工夫を重ねることで、信頼関係の構築がよりスムーズになります。

営業クレーム対応で避けたい落とし穴
営業現場でクレーム対応を行う際、避けるべき落とし穴がいくつか存在します。まず、「責任転嫁」や「曖昧な説明」は絶対に避けるべきです。これらはお客様の不信感を招き、状況を悪化させる原因となります。
また、感情的になったり、相手の主張を否定する対応もNG例としてよく挙げられます。たとえば、「うちのミスではありません」と即断するのではなく、事実確認を徹底し、冷静に状況を説明することが重要です。返金や値引き要求があった場合も、安易に応じるのではなく、会社の方針や理由を丁寧に伝えましょう。
さらに、クレーム対応後のフォローを怠ると、顧客満足度が大きく低下します。「対応したから終わり」ではなく、解決後も定期的に連絡し、顧客の気持ちをケアすることが、今後の営業活動に良い影響を与えます。
クレーム対応が営業成績に与える影響とは

営業クレーム対応が成績に直結する理由
営業活動においてクレーム対応は、成績に直結する非常に重要な要素です。なぜなら、クレームが発生した場合の対応次第で顧客の満足度や信頼度が大きく左右されるためです。適切な対応を行えば、顧客がリピートや紹介につながりやすく、営業成績の向上が期待できます。
例えば、クレーム発生時に迅速な謝罪や原因の説明、解決策の提示を行うことで、お客様は「この会社(担当者)は信頼できる」と感じやすくなります。一方で、対応が遅い・不誠実であれば、不満が増幅し取引停止や悪評拡散のリスクも高まります。営業においてクレーム対応が成績を左右する理由は、このように顧客との信頼関係の構築や維持に直結しているからです。

営業現場でクレーム対応が評価される訳
営業現場では、クレーム対応の巧拙が個人の評価やキャリアに影響します。その理由は、クレーム対応を通じて顧客対応力や課題解決力、柔軟性などが明確に表れるためです。特に管理職や上司は、クレーム対応の現場での対応を重視し、営業マンの総合力を評価する傾向があります。
実際、クレーム対応が上手い人は信頼されやすく、重要顧客や大きな案件を任されるケースが多いです。逆に、クレーム対応が苦手な場合は、顧客との関係悪化や取引縮小につながり、営業成績や社内評価にもマイナスとなることが少なくありません。したがって、営業現場でクレーム対応が評価されるのは、営業職に求められる基礎力が凝縮されているからです。

クレーム対応で営業成績を伸ばす秘訣
クレーム対応で営業成績を伸ばすためには、いくつかのポイントを意識することが重要です。まず、クレーム発生時には誠実な謝罪と迅速な対応を心がけ、顧客の感情をしっかり受け止めることが大切です。そのうえで、事実確認と原因特定を行い、明確な解決策を提示することで顧客の信頼回復につなげられます。
具体的には、
・クレーム内容を丁寧にヒアリングし、感情的な反応を避ける
・非がない場合でも、まずは顧客の立場に立って共感を示す
・社内共有を徹底し、再発防止策を明示する
といったプロセスを徹底することが営業成績の向上に役立ちます。これらを実践することで、クレーム対応が新たな信頼構築や営業機会の創出につながるでしょう。

営業クレーム対応の失敗が招くリスク
営業現場でクレーム対応に失敗すると、重大なリスクが発生します。最も大きなリスクは顧客との信頼喪失であり、それによって取引中止や売上減少、悪評拡散につながることがあります。特に、クレーム対応が遅い・誠意が感じられない場合、顧客の不満はさらに大きくなります。
また、クレーム対応の不備は社内評価の低下や担当変更、場合によっては自身のメンタルヘルスへの悪影響も引き起こします。例えば、返金や値引きの要求に対して適切な説明や断り方をせずに対応した場合、他の顧客にも同様の要求が広がるリスクがあります。営業としての信頼を守るためにも、クレーム対応の失敗がもたらすリスクを正しく認識し、慎重に対応することが必要です。

営業でクレームを気にしない心の持ち方
営業職はクレームがつきものですが、それを過度に気にしすぎるとストレスが増大し、営業活動に悪影響を及ぼします。クレームを必要以上に引きずらない心の持ち方としては、「クレームは成長の機会」と捉えることが大切です。失敗や指摘を自己否定と捉えず、今後の改善材料として前向きに受け止めましょう。
具体的には、
・クレーム内容を客観的に分析し、個人攻撃として受け取らない
・社内で相談し、ノウハウや対応例を共有する
・失敗事例から学び、次回に活かす意識を持つ
といった方法が有効です。営業クレーム対応に悩む方も、落ち込むのではなく、経験を積み重ねることで自信と成長につなげることができます。
困難な営業クレームを乗り越える思考法

営業クレーム対応で折れない心を育てる
営業現場では、クレームは避けて通れない課題です。クレーム対応において心が折れそうになることもありますが、営業担当者として成長するためには、折れない心を育てることが重要です。まずは、クレームを個人攻撃と捉えず、業務上の課題として冷静に受け止める視点を持ちましょう。
感情的にならず事実や原因を整理し、対応のポイントを明確にすることで、自分の成長機会と捉えることができます。また、顧客の不満や怒りの背景を理解し、誠実な謝罪や説明を行うことで、信頼関係の再構築にもつながります。
実際に、クレーム対応を通じて「自分の課題が明確になり、営業スキルが向上した」と感じる方も多くいます。困難な状況を乗り越えた経験が、今後の営業活動において自信や強みとなるでしょう。

営業で困難なクレームと向き合う方法
営業活動において特に厄介なクレームは、返金や値引き、返金要求など具体的な金銭的要求が絡むケースです。このような場合、まずは顧客の主張や不満を十分に傾聴し、事実関係や原因を丁寧に確認することが大切です。
その上で、企業や自社のルール、サービス内容を説明しながら、誤解や感情的な部分には冷静に対応しましょう。例えば、返金や値引きが難しい場合は、断る理由を明確に伝えつつ、代替案や今後のサポートを提案するのが効果的です。
「クレーム対応が上手い人」は、こうした困難な状況でも相手の感情を受け止めつつ、事実とルールに基づいた対応を徹底しています。営業担当者として、ケースごとの対応方法を学び、実践で活かす姿勢が信頼構築に直結します。

営業クレームで落ち込む時のリカバリー術
営業でクレーム対応を終えた後、「自分の対応は間違っていなかったか」「また同じことが起きたらどうしよう」と落ち込むことは珍しくありません。こうした時は、感情を整理し、冷静に振り返るリカバリー術が必要です。
まずは、事実と感情を切り分けて記録し、どこに課題があったのか客観的に分析します。必要であれば上司や同僚に相談し、アドバイスやフィードバックをもらうことで視点を広げましょう。失敗を責めるのではなく、次回に活かすための改善点を見つけることが大切です。
実際に「クレーム対応で落ち込む」ことが多い営業マンも、周囲との情報共有や自己分析を続けることで、気持ちの切り替えや成長を実感しています。落ち込みを長引かせず、次の営業活動に前向きに取り組む姿勢が成果につながります。

営業クレーム対応のストレス軽減法とは
クレーム対応は精神的なストレスが大きく、営業マンにとって大きな負担となります。ストレスを軽減するためには、感情を溜め込まずに適切に発散する方法を身につけましょう。例えば、同僚との情報交換や、定期的な休憩、趣味の時間を確保することが効果的です。
また、クレーム対応の流れやポイントをマニュアル化し、対応方法を標準化することで、精神的な負担を減らせます。自分だけで抱え込まず、組織として支え合う仕組みを活用することも大切です。
実際、「営業 クレーム対応 ストレス」で悩む方も多いですが、ストレスマネジメントを意識した働き方を実践することで、メンタルヘルスの維持や営業成績の向上にもつながります。

営業で非がない場合の対応ポイント
営業活動では、必ずしも自社や自分に非がない場合でも、クレームに直面することがあります。その際は、感情的に反論するのではなく、まずは顧客の話に耳を傾け、相手の気持ちを受け止める姿勢が重要です。
次に、事実関係を丁寧に確認し、もし誤解や情報不足が原因であれば、冷静かつ分かりやすく説明を行いましょう。必要に応じて、上司や関係部門と連携し、組織としての対応方針を確認することも大切です。
「クレーム対応 非がない場合」には、納得感のある説明や、今後のサポート体制を提案することで、顧客との信頼関係を維持できた事例も多くあります。顧客満足度向上のため、誠実な対応を心がけましょう。
顧客満足へ導く営業の共感力と解決力

営業クレームで共感を示す伝え方の工夫
営業現場でクレームが発生した際、まず重要なのは顧客の感情にしっかり寄り添い、共感を言葉で伝えることです。クレーム対応では「ご不便をおかけし申し訳ありません」「お気持ちを察します」といった共感のフレーズが大きな効果を発揮します。こうした一言があるだけで、顧客は自分の不満や怒りを理解してもらえたと感じ、心が和らぎやすくなります。
共感を示す際は、相手の話を最後まで傾聴し、事実確認を急がず感情の受け止めを優先しましょう。たとえば「お話を伺い、状況を理解いたしました」と伝えることで、顧客は安心感を持ちます。共感が伝わらないと、顧客は「この担当者は自分の気持ちを分かっていない」と不信感を抱くリスクもあるため注意が必要です。

営業で顧客満足を高める解決力の磨き方
クレーム対応で顧客満足度を高めるには、迅速かつ的確な解決力が求められます。問題発生時は、まず事実関係を正確に把握し、原因を明確にすることがポイントです。その上で、可能な対策や代替案を複数提示することで、顧客に選択肢を持たせられます。
具体的な解決策を提示する際は「ご指摘いただいた部分を至急確認し、必要に応じて返金や再対応を検討します」といったように、行動計画を明示しましょう。とくに返金や値引き要求があった場合は、社内規定やサービス内容を丁寧に説明し、納得感を持っていただくことが重要です。成功体験として、「迅速な対応で顧客の信頼を取り戻せた」「複数案を提示し納得してもらえた」といった声も多く、解決力を磨くことでリピート受注や紹介につながるケースが増えています。

営業クレーム対応で信頼が深まる瞬間
クレーム対応で顧客の信頼が深まる瞬間は、誠実な対応とフォローアップが評価されたときです。たとえば、謝罪や説明だけでなく「今後は同様の問題が起こらぬよう対策を徹底します」と伝え、実際に改善策を実施することで、顧客は企業や営業担当者の真摯な姿勢を感じ取ります。
また、クレーム解決後も定期的な連絡やアフターフォローを行うことで、「この会社は自分のことを大切にしてくれている」との印象を持ってもらえるでしょう。失敗例として、対応が遅れたり表面的な謝罪だけで終わった場合は、逆に信頼を損なうリスクが高まります。信頼構築には日々の積み重ねが不可欠であり、クレーム対応を通じて関係がより強固になることも少なくありません。

営業で顧客の感情理解が重要な理由
営業において顧客の感情を理解することは、クレーム対応の成功に直結します。なぜなら、顧客が抱える不満や怒りの根底には、サービスや対応に対する「期待」があるからです。その期待に寄り添う姿勢を示すことで、単なる問題解決にとどまらず、顧客満足や信頼獲得につながります。
顧客の感情を無視して事務的な対応に終始すると、「自分の気持ちが伝わっていない」と感じられ、さらにクレームが拡大することもあります。逆に、感情を受け止め「ご不安な気持ち、よく分かります」と伝えるだけで、顧客は安心して話を進められるようになります。感情理解を意識した対応は、営業現場でのストレス軽減や長期的な信頼関係構築にも寄与します。

営業クレーム対応の最強の話し方実践例
営業クレーム対応で最強とされる話し方の実践例として、まず「傾聴」「共感」「説明」「提案」の4つのステップを意識することが挙げられます。具体的には「まず詳しくお話をお聞かせください」と傾聴姿勢を示し、「ご不便をおかけし申し訳ありません」と感情に共感します。
次に、事実や原因を丁寧に説明し、「今後どう改善するか」や「どのような対応が可能か」を提案することで、顧客の納得感が高まります。NG例として、責任転嫁や言い訳、感情的な反論は避けましょう。上手な人は、相手の話をさえぎらず事実を整理し、冷静かつ誠実に対応しています。こうした話し方を身につけることで、営業現場でのストレスも軽減でき、結果的に顧客満足度の向上へとつながります。
非がない場合でも活きる営業対応術

営業で非がないクレームの対処方法
営業活動の中で、自社や自分に明らかな非がないにもかかわらずクレームを受ける場面は少なくありません。こうした場合でも、クレーム対応の基本は「お客様の感情を受け止め、真摯に向き合う姿勢」を持つことです。事実関係を丁寧にヒアリングし、感情的にならずに冷静に対応することが信頼構築の第一歩となります。
なぜなら、お客様は必ずしも事実のみでなく「不満」や「不安」からクレームを申し出ることが多いためです。例えば、納期遅延がなかったにもかかわらず「遅い」と感じて連絡してくるケースでは、まず「ご心配をおかけし申し訳ございません」と気持ちに寄り添う言葉を伝えましょう。その後、客観的な記録や事実を一緒に確認し、誤解を解くことが重要です。
このようなクレーム対応の際は、決して相手の主張を頭ごなしに否定せず、あくまで「事実確認」と「感情のケア」を両立させることがポイントです。結果として、顧客は「誠意ある対応」と受け取り、営業担当者への信頼が高まる傾向があります。

営業クレーム返金要求を断る伝え方
営業現場では、返金要求という厳しいクレームに直面することがあります。返金が適切でない場合でも、断る際には「納得感」と「誠実さ」を両立させる伝え方が欠かせません。最初に、相手の話を遮らずに最後まで聞き、返金要求の理由や背景を丁寧に確認しましょう。
その上で、返金ができない理由を具体的かつ明確に説明します。たとえば「契約内容に基づき、今回は返金の対象外となります」と事実を示した上で、「ご不快な思いをさせてしまい申し訳ありません」と謝罪の意も忘れず伝えます。返金以外の解決策(商品の交換やアフターサービスの強化など)を提案することで、顧客の不満を和らげることが可能です。
返金を断る際は、感情的な対立を避け、冷静かつ丁寧な対応を心掛けましょう。実際の現場でも、「断られたけど誠実に説明してもらえたので納得できた」という声が多く、信頼回復に繋がるケースがあります。

営業で値引き要求を受けた際の対応法
営業活動では、顧客から値引き要求を受けることも多いですが、安易な値引きは自社や自身の信頼を損なうリスクがあります。まずは、なぜ値引きを希望しているのか理由を確認し、顧客の立場や背景に理解を示すことが重要です。
その上で、商品の価値やサービス内容を再度説明し、価格の根拠を明確に伝えることがポイントです。例えば「高品質なアフターサービスが含まれているため、この価格設定となっております」と根拠を示しましょう。どうしても値引きが難しい場合は、今後の取引での特典や別の付加価値提案を行い、納得感を高める工夫も有効です。
値引き要求への対応を誤ると、「この営業担当には強く言えば通る」と思われ、以後の交渉が難航することがあります。毅然としつつも柔軟な姿勢を持つことが、長期的な信頼関係の構築に繋がります。

営業クレーム対応で中立性を保つコツ
クレーム対応の際には、営業担当者として「お客様」と「自社」の間で中立性を保つことが不可欠です。どちらかに偏りすぎると、誤解や不信感を招く可能性があります。まずは事実を冷静に確認し、感情的な発言は避けるよう心掛けましょう。
中立性を保つためには、「事実ベースの説明」と「双方の立場を理解する姿勢」が大切です。例えば「お客様のお気持ちは理解できますが、当社のシステム上このような対応となってしまいました」と、両者の意見や状況をバランスよく伝えることが有効です。必要に応じて第三者(上司や専門部署)の意見を仰ぐのも一つの方法です。
中立性を意識した対応は、顧客だけでなく社内からの信頼獲得にも繋がります。経験豊富な営業担当者ほど、感情的にならず冷静な判断を重視しており、長期的な営業活動において大きな強みとなります。

営業現場で冷静に対応するポイント
クレーム対応で最も重要なのは、どんな状況でも冷静さを保つことです。感情的な反応は顧客の不満を増幅させるだけでなく、自分自身のストレスや営業成績にも悪影響を及ぼします。深呼吸や一呼吸置く習慣をつけることで、冷静な対応がしやすくなります。
また、事実関係を整理し、感情と事実を切り分けて考えることがポイントです。例えば、顧客の怒りの言葉に反応するのではなく、「なぜそのように感じられたのか」背景を丁寧に確認します。必要に応じて上司や同僚のサポートを仰ぐのも有効です。
冷静な対応を実践することで、「クレーム対応が上手い人」と評価されやすくなり、結果的に営業現場での信頼や評価も高まります。実際に、現場で冷静に対応できる営業担当者は、顧客からのリピートや紹介を得やすい傾向にあります。